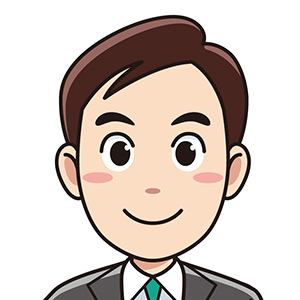※この記事にはプロモーションが含まれています。

勝手に借金の連帯保証人にさせれられていた場合、基本的にその契約は法的に無効です。
書類を偽造したり、サインを勝手に書いたりするのは立派な犯罪行為であり、ある重大な罪が適用されます。
ただ、債権者との話がこじれると裁判にまで発展し、場合によっては敗訴してしまうケースもあります。
ここでは知らない間に連帯保証人になっていた人が債権者から支払いを請求された場合の対処法について解説をしていきます。
目次
勝手に保証人にしたら何の罪が適用される?

まず、債務者が連帯保証人を立てて、債権者と契約を結ぶ際、連帯保証人に確認をせず、連帯保証人となる本人が署名(サイン)や押印をしていなかった場合、その契約は無効となります。
債務者は書類を偽造しているからです。
また、債務者が連帯保証人の代わりに勝手にサインをすることは無権代理行為と呼ばれています。
さらに、刑法上は、有印私文書偽造罪や有印私文書行使罪となり、3年以上5年以下の刑事罰の対象となることが刑法第159条1項で定められています。
刑法第159条
1. 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
つまり、勝手に連帯保証人にすることは立派な犯罪行為となるのです。
親・兄弟でも罪になる
もし、勝手に連帯保証人にしたのが、親や兄弟でもあった場合でも、有印私文書偽造罪や有印私文書行使罪の例外となることはありません。
この罪で被害を受けるのは、あくまでも債権者だからです。
ですから相手は誰であれ、勝手に連帯保証人にされた場合は、その罪を訴えることが可能です。
借金の返済義務を要求された場合の対処法
勝手に連帯保証人にさせられていた場合、契約は原則、無効なので返済義務はありません。
しかし、元々の債務者が支払い不能となり、債権者から連帯保証人としての支払いを求められた場合、ただ、放置しているだけではダメです。
自分は知らない間に連帯保証人にさせられていたことを債権者に対してきちんと伝える必要があるからです。
では、具体的にどういった対処法を取っていけば良いのでしょうか?
1円も支払ってはいけない

債権者から連帯保証人になっているから借金を支払うように言われた時、絶対やってはいけないことは、1円でも返済をしてしまうことです。
その場合は、連帯保証人であることを追認したこととなり、借金に対する返済義務が正式に発生してしまうからです。
ですから、どんなことを言われても、支払いは拒否して下さい。
契約書のコピーを送ってもらう

次に、やるべきなのは、あなたがどういった形で勝手に連帯保証人にさせられているのか実情を把握するために、債権者から契約書のコピーを送ってもらうことです。
そこで、
- 署名の部分で勝手にサインされていないか(偽造のサインではないか)
- 押印が実印になっていないか
という点をチェックして下さい。
内容証明郵便を送る

契約書のコピーを確認して、やはり自分の個人情報や署名を勝手に書かれたものであることが判明した場合、債権者に対して、内容証明の郵便を送って下さい。
そこで、
- 連帯保証人にはなった覚えはない
- 支払いを一切拒否する
- 今後、返済の要求はしないで欲しい
という旨をしっかり記載します。
内容証明郵便で送る理由は、万が一裁判に発展した場合に証拠として使うためです。
これで、債権者が納得して、支払いを要求する連絡をしなくなればそれで終わりです。
しかし、債権者側としては、そうなってしまうと泣き寝入りで終わってしまうので、それでも連帯保証人としての契約は有効だと主張してくる場合があります。
その場合は、裁判という形で決着をする必要が出て来ます。
裁判になった場合のポイントは?

裁判で、勝手に借金の連帯保証人にさせられていた人は、債務不存在確認請求(自分には債務が存在しないことの確認を求める)をするようになります。
そこでのポイントは、契約で勝手に連帯保証人にさせられていたことを法的にいかに証明できるかという点になってきます。
もし、連帯保証人のハンコがシャチハタであったり、署名(サイン)を代筆したりしていたようなケースでは、自分の意志はなかったことを証明しやすくなるでしょう。
しかし、ここで実印が押されていたり、印鑑証明が提出されたりしていた場合は非常に厄介となり、場合によっては裁判に負ける可能性も出て来ます。
実際、債務者が勝手に連帯保証人にされた場合、あなたも被害者ですが、債権者も被害者です。
ですから、実質、被害者同士の裁判となるため、あなたが敗訴することもあり得るのです。
ただ、それでも債権者としては借金の連帯保証人となる本人に確認を行っていたという点で落ち度があるのでその点はしっかり主張をしていく必要があります。
弁護士に依頼をした場合の費用は?

実際、状況によっては裁判で負けてしまう場合もあり、確実に裁判で勝訴するために弁護士に依頼することをオススメいたします。
その場合、弁護士の費用としては、着手金や報酬金として数十万円ぐらい掛かるケースも出て来ます。
勝手に連帯保証人にされられたのに、それだけの費用が掛かるの不合理だと感じてしまうかもしれません。
ただ、裁判に負けると、場合によっては、数百万円の支払いを求められ、自己破産に追い込まれるケースもあります。
ですから、そういった甚大な被害を防ぐためにも弁護士に依頼をすることも一つの選択肢だと言えます。
連帯保証人にされたことを無効にした後は

もし、連帯保証人にされたことを無効にすることができたら、当然、債務者本人は窮地に追い込まれるでしょう。
もちろん、あなたを勝手に連帯保証人にした人ですから、その人がどうなろうか、知ったことではないということもできるかと思います。
ただ、相手は、あなたの全く知らない人ではなく、あなたとある程度、親しかった友人や知人、或いは、親など親族であるケースも多いものです。
そういった身近な人が、借金で苦しむのは、ちょっと可哀そうだと思った場合は、債務整理の手続きをするよう勧めてみるのはいかがでしょうか。
>>借金の負担を減らす方法、簡単チェック【所要時間1~2分】
「罪を憎んで人を憎まず」とも言われますが、いざという時は、上記のサービスを紹介してみて下さい。
まとめ
勝手に連帯保証人になっていた場合、その契約は原則無効ですし、勝手にサインをしたり、書類を偽造したりすることは明らかな犯罪行為なので、親、兄弟であれ、訴えることも可能です。
ただ、債権者に対しては、勝手に連帯保証人にされたことを、きちんと証明する必要があります。
実際、実印が押されたりしていると、敗訴する可能性も出てくるので、心配な方は弁護士に相談するのも一つの方法です。

借金問題の相談に関しては、無料で対応している弁護士も多いので、状況に応じて、相談してみて下さい。